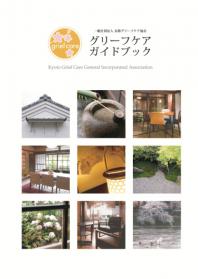- ホーム
- 協会からのお知らせ
協会からのお知らせ
2014/12/11
「悲しみに寄り添うために ―周産期の緩和ケアとグリーフケア― 」のテーマで第8回公開講座が開催されました。

2014年12月7日(日)協会にて公開講座が開講されました。
講師は和田浩先生(大阪発達総合療育センター訪問診療課・小児科)です。
先生は淀川キリスト教病院 小児科副部長、周産期母子センター長として新生児・周産期領域でお勤めになっていましたが、この春からは小児の訪問医療医師として活動されています。まだまだ小児の訪問医療医師が少ないためか和田先生の活動を聞き、驚かれる方や感激されている方などが見られました。今回のテーマは、新生児・周産期領域が中心でした。内容はもちろん、先生の優しく、また柔らかな語り口調も好評でした。
参加者のアンケートを一部下記に抜粋します。
○NICUのグリーフケアに携わっているので、具体的な講義が自分の実践と重なって、すごく理解できました。質疑の時間もゆっくり取って頂いたので、充実した時間でした。NICU遺族会のファシリテーターとしてグリーフケアに取り組んでいるので、活用していきたいと思います。
○現在、まさに自分自身が実践しているテーマでしたので、より深い学びになったと思います。周産期領域の状況もどんどん変化するため、私自身、そして周産期のスタッフがその背景をしっかりと理解しながら関わらせて頂きたいと思います。知識的なところでも、理論的なところでも、しっかり学んでいけたように感じます。
○周産期のグリーフケアの「柱」を改めて認識できた。様々な立場の方の話を交えた、参加者同士の話(実体験や悩んでいること)、先生の話、共に実感できました。
NICUのチーム医療が持つべき姿勢を再認識できたので、情報共有していきたい。
○グリーフケアを「子どもを亡くした家族」だけが対象ではなく、今の在宅看護のすべての家族が対象と学べて自分の役割が再確認できました。物腰がソフトで、こんな小児科医ばかりならいいなと思います。
○産科・NICUで今やっていることは間違いないんだと思わせてくれました。やりがいを感じています。もっと早く受講すれば良かったです。とてもおだやかなお声で、本などでいつも拝見していますが、その点も良かったです。
講師の和田先生、そして受講者の皆さま、寒い中お越しいただきありがとうございました。

2014年12月7日(日)協会にて公開講座が開講されました。
講師は和田浩先生(大阪発達総合療育センター訪問診療課・小児科)です。
先生は淀川キリスト教病院 小児科副部長、周産期母子センター長として新生児・周産期領域でお勤めになっていましたが、この春からは小児の訪問医療医師として活動されています。まだまだ小児の訪問医療医師が少ないためか和田先生の活動を聞き、驚かれる方や感激されている方などが見られました。今回のテーマは、新生児・周産期領域が中心でした。内容はもちろん、先生の優しく、また柔らかな語り口調も好評でした。
参加者のアンケートを一部下記に抜粋します。
○NICUのグリーフケアに携わっているので、具体的な講義が自分の実践と重なって、すごく理解できました。質疑の時間もゆっくり取って頂いたので、充実した時間でした。NICU遺族会のファシリテーターとしてグリーフケアに取り組んでいるので、活用していきたいと思います。
○現在、まさに自分自身が実践しているテーマでしたので、より深い学びになったと思います。周産期領域の状況もどんどん変化するため、私自身、そして周産期のスタッフがその背景をしっかりと理解しながら関わらせて頂きたいと思います。知識的なところでも、理論的なところでも、しっかり学んでいけたように感じます。
○周産期のグリーフケアの「柱」を改めて認識できた。様々な立場の方の話を交えた、参加者同士の話(実体験や悩んでいること)、先生の話、共に実感できました。
NICUのチーム医療が持つべき姿勢を再認識できたので、情報共有していきたい。
○グリーフケアを「子どもを亡くした家族」だけが対象ではなく、今の在宅看護のすべての家族が対象と学べて自分の役割が再確認できました。物腰がソフトで、こんな小児科医ばかりならいいなと思います。
○産科・NICUで今やっていることは間違いないんだと思わせてくれました。やりがいを感じています。もっと早く受講すれば良かったです。とてもおだやかなお声で、本などでいつも拝見していますが、その点も良かったです。
講師の和田先生、そして受講者の皆さま、寒い中お越しいただきありがとうございました。
2014/11/17
2014年11月16日(日)第2回看護師・助産師さま向け公開セミナーが、京都知恩院 和順会館にて開催されました。

公開セミナーは2部構成で、それぞれ1時間40分ずつの講義です。
○第一部
講師:沼野 尚美先生/宝塚市立病院 緩和ケア病棟 チャプレン・カウンセラー)
テーマ:「グリーフを小さくするための事前ケア」
○第二部
講師:梶山 徹先生/関西電力病院 緩和医療科部長・心療内科部長(兼務)
テーマ:「がんのスピリチュアルケアとグリーフケア」
●受講者のアンケートを一部紹介します。----------------------------
〜第1部〜 沼野尚美先生
○講義という感じではなく、とてもリラックスして受講することができた時間でした。ユーモアのある話しぶりで宝塚市立病院などでの実際をお聞きできて楽しかったです。今は訪問看護で病棟勤務から遠のいていますが、個々に関わることが多い中、対応する直接的な言葉かけが聞けたと思います。みんな同じことで悩んでいるんだと再認識しました。
○具体的なケースをたくさん教えていただきました。どのように関わっていけばいいか具体的に知る事ができ実践できる内容でした。ありがとうございます。
○実話を交えとても興味深い内容でした。今まで先生のご本・CDなどで存じ上げていましたが、やはりライブではとても迫力がありました。
○おもしろおかしく、ぐっとくる話が聞けて良かった。沼野先生の講義は何度か受けたが、こんなに近距離で先生の話が聞け、感激しました。
○自分自身9年前に母を亡くし後悔が残っています。これから自分が関わる家族が、少しでもグリーフが小さく過ごしていけるよう、まずは患者さんと家族の思いをしっかりと理解していきたいです。その上で、今日お話して頂いた具体的な関わりについて、何をしていけば良いのか考え、対象に応じた関わりができると良いと思いました。
〜第2部〜 梶山 徹先生
○スピリチュアルケアの理解があった上で、グリーフケアがなされるという点、傾聴して共感するということに対して、自分の思い違いがあったことがわかり今後援助する上で自分の姿勢に気付くことができた。
○世の中に万延している怪しいスピリチュアルのことがあったので、スピリチュアルという言葉はあまり表現してきませんでしたが、今日講座を聞いてとてもよくわかりました。明日より実践していこうと思います。
○傾聴・ナラティブなど、できることから職場でやっていこうと思った。希望実現のため患者が目標を決められるように関わっていこうと思った。
年齢を重ねてきて、色んなこと(身の回りに起こることなど)全て意味のあとだと感じるようになった。
○スピリチュアルケア・グリーフケアのGOSや共感の考え方など改めて理解することができた。傾聴技法など具体的な方法も分かりやすく教えて頂けたので実際に活用できるようにしたいと思いました。
○患者様主体のケア・心の声によりそうためのコミュニケーション技術など医療従事者としてだけではなく、人としてのあり方を考えさせられました。
あくまで患者様主体、そしてより多くの情報を得るため語ってもらうこと、心がけていきたいです。
------------------------------------------------------------------
紅葉も始まりいい雰囲気になった知恩院に、今回も、全国各地様々な場所から参加して頂きました。
テーマの内容から、緩和ケア病棟の看護師様が多く、他には訪問看護師・看護学校教員・救急・内科などの看護師様もいらっしゃいました。
看護師の方々と患者さん・ご家族との関わりは、患者さんの死後、ご家族のグリーフワークに影響します。
その中で、スピリチュアルペインを意識して寄り添うことの意味と重要性を、再認識できたというお声を
多く頂きました。
知恩院で行う24名の公開セミナーは、今年度分はこれで終了です。
次年度も開催予定ですのでご興味のある方は、定期的に当ホームページをチェック下さい。
それでは皆様お疲れ様でした。また、講演をいただきました沼野先生・梶山先生、ありがとうございました。

公開セミナーは2部構成で、それぞれ1時間40分ずつの講義です。
○第一部
講師:沼野 尚美先生/宝塚市立病院 緩和ケア病棟 チャプレン・カウンセラー)
テーマ:「グリーフを小さくするための事前ケア」
○第二部
講師:梶山 徹先生/関西電力病院 緩和医療科部長・心療内科部長(兼務)
テーマ:「がんのスピリチュアルケアとグリーフケア」
●受講者のアンケートを一部紹介します。----------------------------
〜第1部〜 沼野尚美先生
○講義という感じではなく、とてもリラックスして受講することができた時間でした。ユーモアのある話しぶりで宝塚市立病院などでの実際をお聞きできて楽しかったです。今は訪問看護で病棟勤務から遠のいていますが、個々に関わることが多い中、対応する直接的な言葉かけが聞けたと思います。みんな同じことで悩んでいるんだと再認識しました。
○具体的なケースをたくさん教えていただきました。どのように関わっていけばいいか具体的に知る事ができ実践できる内容でした。ありがとうございます。
○実話を交えとても興味深い内容でした。今まで先生のご本・CDなどで存じ上げていましたが、やはりライブではとても迫力がありました。
○おもしろおかしく、ぐっとくる話が聞けて良かった。沼野先生の講義は何度か受けたが、こんなに近距離で先生の話が聞け、感激しました。
○自分自身9年前に母を亡くし後悔が残っています。これから自分が関わる家族が、少しでもグリーフが小さく過ごしていけるよう、まずは患者さんと家族の思いをしっかりと理解していきたいです。その上で、今日お話して頂いた具体的な関わりについて、何をしていけば良いのか考え、対象に応じた関わりができると良いと思いました。
〜第2部〜 梶山 徹先生
○スピリチュアルケアの理解があった上で、グリーフケアがなされるという点、傾聴して共感するということに対して、自分の思い違いがあったことがわかり今後援助する上で自分の姿勢に気付くことができた。
○世の中に万延している怪しいスピリチュアルのことがあったので、スピリチュアルという言葉はあまり表現してきませんでしたが、今日講座を聞いてとてもよくわかりました。明日より実践していこうと思います。
○傾聴・ナラティブなど、できることから職場でやっていこうと思った。希望実現のため患者が目標を決められるように関わっていこうと思った。
年齢を重ねてきて、色んなこと(身の回りに起こることなど)全て意味のあとだと感じるようになった。
○スピリチュアルケア・グリーフケアのGOSや共感の考え方など改めて理解することができた。傾聴技法など具体的な方法も分かりやすく教えて頂けたので実際に活用できるようにしたいと思いました。
○患者様主体のケア・心の声によりそうためのコミュニケーション技術など医療従事者としてだけではなく、人としてのあり方を考えさせられました。
あくまで患者様主体、そしてより多くの情報を得るため語ってもらうこと、心がけていきたいです。
------------------------------------------------------------------
紅葉も始まりいい雰囲気になった知恩院に、今回も、全国各地様々な場所から参加して頂きました。
テーマの内容から、緩和ケア病棟の看護師様が多く、他には訪問看護師・看護学校教員・救急・内科などの看護師様もいらっしゃいました。
看護師の方々と患者さん・ご家族との関わりは、患者さんの死後、ご家族のグリーフワークに影響します。
その中で、スピリチュアルペインを意識して寄り添うことの意味と重要性を、再認識できたというお声を
多く頂きました。
知恩院で行う24名の公開セミナーは、今年度分はこれで終了です。
次年度も開催予定ですのでご興味のある方は、定期的に当ホームページをチェック下さい。
それでは皆様お疲れ様でした。また、講演をいただきました沼野先生・梶山先生、ありがとうございました。
2014/10/27
2014年10月26日(日) 第3回 公開講座が京都グリーフケア協会にて開催されました。

講師は船戸正久先生(大阪発達総合療育センター副センター長)です。
「新生児・小児の看取りのケア こどもの人権と尊厳を守るための協働意思決定と事前ケアプランの重要性」のテーマで講演頂きました。
今回の参加者は、助産師の方など母子に関わる方がほとんどで、胎児緩和ケアなど深いテーマでも、同じ領域同士で議論が進められ、より学びを深められたことと思います。授業修了後も、参加者同士で授業テーマについて話を続けられており、皆様の熱意や思いが肌で感じられました。
参加者のアンケートを一部下記に抜粋します。
○助産師など、それぞれの立場での現場の話を聞けてよかった。協働意志決定の重要性を感じました。医療者と家族が協働意志決定できるよう家族との会話の中で意志をくみとり医療者間での話し合いがもてるようにしていきたいです。
○胎児緩和ケアを初めて知りました。今の職場ではできるだけの医療をしながら在宅生活を送っておられる方がほとんどで、治療を中止すること、正常の医療の範疇など職場で話してみたいと思った。
○現場で周産期・小児科の倫理的意思決定支援を実践することが多く、グリーフケア(死産などのご家族対象)外来を担当しておりますので、タイムリーでした。また職場の倫理委員会のことも質問できて良かったです。
○新生児・胎児緩和ケアなど悩んでいる部分が、概念的にも新しい知識としても得ることができた。できる限り後輩に情報提供してケアの質を高めたいと思います。
講師の船戸先生、そして受講者の皆さま、本当にありがとうございました。

講師は船戸正久先生(大阪発達総合療育センター副センター長)です。
「新生児・小児の看取りのケア こどもの人権と尊厳を守るための協働意思決定と事前ケアプランの重要性」のテーマで講演頂きました。
今回の参加者は、助産師の方など母子に関わる方がほとんどで、胎児緩和ケアなど深いテーマでも、同じ領域同士で議論が進められ、より学びを深められたことと思います。授業修了後も、参加者同士で授業テーマについて話を続けられており、皆様の熱意や思いが肌で感じられました。
参加者のアンケートを一部下記に抜粋します。
○助産師など、それぞれの立場での現場の話を聞けてよかった。協働意志決定の重要性を感じました。医療者と家族が協働意志決定できるよう家族との会話の中で意志をくみとり医療者間での話し合いがもてるようにしていきたいです。
○胎児緩和ケアを初めて知りました。今の職場ではできるだけの医療をしながら在宅生活を送っておられる方がほとんどで、治療を中止すること、正常の医療の範疇など職場で話してみたいと思った。
○現場で周産期・小児科の倫理的意思決定支援を実践することが多く、グリーフケア(死産などのご家族対象)外来を担当しておりますので、タイムリーでした。また職場の倫理委員会のことも質問できて良かったです。
○新生児・胎児緩和ケアなど悩んでいる部分が、概念的にも新しい知識としても得ることができた。できる限り後輩に情報提供してケアの質を高めたいと思います。
講師の船戸先生、そして受講者の皆さま、本当にありがとうございました。
2014/10/20
2014年10月19日(日) 第6回 公開講座が京都グリーフケア協会にて開催されました。

講師は細井 順先生(ヴォーリズ記念病院ホスピス長)です。
「“かなしみ”に寄り添うケア」のテーマで講演頂きました。
DVDの視聴をはじめ、参加者の皆さまに臨床に即した課題や抱えている問題を話して頂き、それをテーマに話を深めていく参加型の講義が行われました。
初めは緊張していた参加者も細井先生の時にユーモアを交えた穏やかな口調と温かい雰囲気に引き込まれ、これまで言葉にできなかったことや考えを話され、いつしか参加者同士、熱いディスカッションが行われました。
細井先生の温かいアドバイスや参加者の様々な経験談等、時には涙あり笑いありであっという間の4時間でした。
参加者のアンケートを一部下記に抜粋します。
○カンファレンス時における、心構え(職種として参加するのではなく、人として参加する)が心に響きました。どうしても職種を意識していしまい、原点にあるべき大切な気持ちを忘れていたように思いました。
○参加者同士でディスカッションができたことが非常に良かった。日々悩んでいることを言葉にでき、意見をもらえたことがとても良かった。
○自分の中の心の整理ができた。患者への対応の振り返りができた。
○参加者の皆さまのそれぞれの立場からの話を聞く事ができてとても身近に感じることができました。家族の立場や医療者と別の視点での意見が聞けてとても良かったです。
講師の細井先生、そして受講者の皆さま、本当にありがとうございました。

講師は細井 順先生(ヴォーリズ記念病院ホスピス長)です。
「“かなしみ”に寄り添うケア」のテーマで講演頂きました。
DVDの視聴をはじめ、参加者の皆さまに臨床に即した課題や抱えている問題を話して頂き、それをテーマに話を深めていく参加型の講義が行われました。
初めは緊張していた参加者も細井先生の時にユーモアを交えた穏やかな口調と温かい雰囲気に引き込まれ、これまで言葉にできなかったことや考えを話され、いつしか参加者同士、熱いディスカッションが行われました。
細井先生の温かいアドバイスや参加者の様々な経験談等、時には涙あり笑いありであっという間の4時間でした。
参加者のアンケートを一部下記に抜粋します。
○カンファレンス時における、心構え(職種として参加するのではなく、人として参加する)が心に響きました。どうしても職種を意識していしまい、原点にあるべき大切な気持ちを忘れていたように思いました。
○参加者同士でディスカッションができたことが非常に良かった。日々悩んでいることを言葉にでき、意見をもらえたことがとても良かった。
○自分の中の心の整理ができた。患者への対応の振り返りができた。
○参加者の皆さまのそれぞれの立場からの話を聞く事ができてとても身近に感じることができました。家族の立場や医療者と別の視点での意見が聞けてとても良かったです。
講師の細井先生、そして受講者の皆さま、本当にありがとうございました。
2014/10/9
9月27日(土)、 第2期 介護・ 福祉従事者コース上級クラスが修了しました。

介護・福祉従事者コース上級は、グリーフ概論を踏まえ、様々な臨床・介護現場で行われているグリーフを意識した、実践的な関わりについて多面的に学びます。
患者・利用者が亡くなった後に提供されるグリーフケア(遺族ケア)に限定せず、広い意味でグリーフケアをとらえ、学んで頂いています。
グリーフケアの定義には「死の前後を問わず、結果として遺族の適応過程にとって何らかの助けになる行為」なども含まれます。
グリーフは大切な人との死別後の悲嘆を指すだけでなく、介護施設におられる死別前の期間も含まれ、その場に受持する介護・福祉従事者の寄り添いはとても大切になるのです。
喪失には生活機能不全からの自尊感情・自己肯定感などの喪失、認知症などで見知った人のイメージの喪失、経験すべき未来の喪失など様々な喪失があります。
伴って、そこに絡む人々の様々な感情が複雑に絡みます。
認知症では、数か月前まで、優しい笑顔と優しい言葉をかけてくれたおばあちゃんが別人のようになり、表情からは笑顔も消える現実を見ると、人はそのおばあちゃんの本来あるべき姿を喪失してしまい、介護する家族の感情は急速に悪化する方向へと進むことでしょう。
これらの感情は死別後に限定されるものではなく、療養生活の中でも本人・家族が自然と抱くものです。
上級コースでは現場を中心に考えながら、プロの介護者として家族やご本人に対してどう寄り添うのかを問い、話し合います。
家族の中には、今後の生活への不安や、亡くなって悲しい反面ほっとするという両価的な感情もあれば、自らの人生に積極的に新しい意味を与え、嘆き・悲しみを乗り越えて行かれる方もいらっしゃいます。
そうした様々な家族の心情を、実際にグリーフを抱えた方と関わってきた講師を中心に受講者も参加して大切にすべき姿勢を育んで頂きます。
また、講義では今後看取りが増加する中、利用者とその家族と接する介護従事者自身の戸惑いにも焦点を当て、人の死を常に感じながら様々なケアを行っている介護従事者自身のケアの必要性も説きます。
長い間一緒に生活をした利用者の看取りに多数寄り添う中で、職業者自身がグリーフを感じることもあり、セルフケアの重要性を理解することもまた大切な気づきとなります。
話しは変わりますが、2030年に今より凡そ40万人も死亡者が増加します。
それは病院でなく介護施設に入居する方や在宅医療を受ける方の増加を示します。
つまり、施設で長期療養後に静かに息を引き取る方が増えるということも指します。
その流れでいうと長期の寄り添いを経験した家族は「すべきことはした」という思いの方と、そうでない様々な方が存在することになります。
介護士など援護者は、可能な限り「すべきことはした」とご家族が思える環境や言葉がけを行なうことが大切になるのだと思います。
ことばでは簡単に思えますが、実際にその場でとっさに介護者ができるものではなく、しっかりとした知識と心の準備をすることこそが大切なのだと思います。
当協会の思いは、少数でもしっかりとグリーフケアの知識と心の思いを持っていただけるプロの職業者を育成することです。
看取りが急増する施設でプロとしてグリーフケアを学んでおきたいという方に、常に最良の講義とカリキュラムをお届できればと考えています。
最後に、修了生の方と話す中でこんな語りが聞かれました。
「少し勉強して私はグリーフケアができる、なんて私は言いたくないし他の人にも言ってほしくない。これからも学び続けたいし、踏まえて利用者と関わっていきたい。図書室、また見せてください(笑)」
人類にとってグリーフは普遍です。
各人が抱くグリーフと、人と人との関わりとしてのグリーフケアは、世の中の流れの中で恣意的に形を変えるでしょう。
その中で私達は、常に人としてどうするかを考えながらグリーフケアを学ぶことが必要なのだと思います。
講師の皆様、受講生の皆様有難うございました。

介護・福祉従事者コース上級は、グリーフ概論を踏まえ、様々な臨床・介護現場で行われているグリーフを意識した、実践的な関わりについて多面的に学びます。
患者・利用者が亡くなった後に提供されるグリーフケア(遺族ケア)に限定せず、広い意味でグリーフケアをとらえ、学んで頂いています。
グリーフケアの定義には「死の前後を問わず、結果として遺族の適応過程にとって何らかの助けになる行為」なども含まれます。
グリーフは大切な人との死別後の悲嘆を指すだけでなく、介護施設におられる死別前の期間も含まれ、その場に受持する介護・福祉従事者の寄り添いはとても大切になるのです。
喪失には生活機能不全からの自尊感情・自己肯定感などの喪失、認知症などで見知った人のイメージの喪失、経験すべき未来の喪失など様々な喪失があります。
伴って、そこに絡む人々の様々な感情が複雑に絡みます。
認知症では、数か月前まで、優しい笑顔と優しい言葉をかけてくれたおばあちゃんが別人のようになり、表情からは笑顔も消える現実を見ると、人はそのおばあちゃんの本来あるべき姿を喪失してしまい、介護する家族の感情は急速に悪化する方向へと進むことでしょう。
これらの感情は死別後に限定されるものではなく、療養生活の中でも本人・家族が自然と抱くものです。
上級コースでは現場を中心に考えながら、プロの介護者として家族やご本人に対してどう寄り添うのかを問い、話し合います。
家族の中には、今後の生活への不安や、亡くなって悲しい反面ほっとするという両価的な感情もあれば、自らの人生に積極的に新しい意味を与え、嘆き・悲しみを乗り越えて行かれる方もいらっしゃいます。
そうした様々な家族の心情を、実際にグリーフを抱えた方と関わってきた講師を中心に受講者も参加して大切にすべき姿勢を育んで頂きます。
また、講義では今後看取りが増加する中、利用者とその家族と接する介護従事者自身の戸惑いにも焦点を当て、人の死を常に感じながら様々なケアを行っている介護従事者自身のケアの必要性も説きます。
長い間一緒に生活をした利用者の看取りに多数寄り添う中で、職業者自身がグリーフを感じることもあり、セルフケアの重要性を理解することもまた大切な気づきとなります。
話しは変わりますが、2030年に今より凡そ40万人も死亡者が増加します。
それは病院でなく介護施設に入居する方や在宅医療を受ける方の増加を示します。
つまり、施設で長期療養後に静かに息を引き取る方が増えるということも指します。
その流れでいうと長期の寄り添いを経験した家族は「すべきことはした」という思いの方と、そうでない様々な方が存在することになります。
介護士など援護者は、可能な限り「すべきことはした」とご家族が思える環境や言葉がけを行なうことが大切になるのだと思います。
ことばでは簡単に思えますが、実際にその場でとっさに介護者ができるものではなく、しっかりとした知識と心の準備をすることこそが大切なのだと思います。
当協会の思いは、少数でもしっかりとグリーフケアの知識と心の思いを持っていただけるプロの職業者を育成することです。
看取りが急増する施設でプロとしてグリーフケアを学んでおきたいという方に、常に最良の講義とカリキュラムをお届できればと考えています。
最後に、修了生の方と話す中でこんな語りが聞かれました。
「少し勉強して私はグリーフケアができる、なんて私は言いたくないし他の人にも言ってほしくない。これからも学び続けたいし、踏まえて利用者と関わっていきたい。図書室、また見せてください(笑)」
人類にとってグリーフは普遍です。
各人が抱くグリーフと、人と人との関わりとしてのグリーフケアは、世の中の流れの中で恣意的に形を変えるでしょう。
その中で私達は、常に人としてどうするかを考えながらグリーフケアを学ぶことが必要なのだと思います。
講師の皆様、受講生の皆様有難うございました。
2014/10/2
10月1日の京都新聞社様朝刊にて、当協会が発行した「グリーフケアガイドブック」の紹介記事が掲載されました。

協会講師の皆様を執筆者に、援助者向けにグリーフケアのガイドブックを発行しましたが、その主旨をご理解頂き取材をしていただけました。
3000冊は援助者が働かれているだろう病院や施設、またグリーフケアを学ばれている医療系大学、図書館などに寄贈しております。
A4版171ページ 税込2160円です。
僅かですが一般にも販売しております。ご希望者はどうぞお問い合わせください。
京都新聞社様には厚く御礼申し上げます。
問合せお申し込み
電話:075−741−7114(京都グリーフケア協会事務局)
インターネットからのお申し込みフォームはこちら

協会講師の皆様を執筆者に、援助者向けにグリーフケアのガイドブックを発行しましたが、その主旨をご理解頂き取材をしていただけました。
3000冊は援助者が働かれているだろう病院や施設、またグリーフケアを学ばれている医療系大学、図書館などに寄贈しております。
A4版171ページ 税込2160円です。
僅かですが一般にも販売しております。ご希望者はどうぞお問い合わせください。
京都新聞社様には厚く御礼申し上げます。
問合せお申し込み
電話:075−741−7114(京都グリーフケア協会事務局)
インターネットからのお申し込みフォームはこちら
2014/9/17
2014年9月7日 京都府主催H26年度ゲートキーパーステップアップ研修にて、藍野大学教授・臨床心理士の足利学先生が、グリーフケアの講義を行われました。

テーマは「グリーフ概論・自死/自殺におけるグリーフ」でした。
グリーフ・グリーフ反応についての概論と基礎的な知識、自死/自殺におけるグリーフを講義され、その後にはグループワークを実施しました。
足利先生の講義の後には、自殺遺族の尾角光美氏(一般社団法人リヴオン代表)が当事者としての内容を、弁護士会・司法書士会の方からは、それぞれの領域で自死/自殺に特化した内容をそれぞれお話されました。多面的に自死を考える大切な場となりました。
受講者の方々は、ゲートキーパー(悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のこと)の方々で、中には臨床心理士の方も多くいらっしゃいました。
ご感想の中で、良かった点として
「初学者でも大変わかりやすい講義でした。」
「ゆっくりていねいに話してもらえてわかりやすかった。」
「事例や実践に基づいた内容で知りたいことを簡潔に資料にまとめていただいていた。」
などのご意見がありました。
今回、お声をいただきました京都府の御関係者、並びに講師をしていただいた足利先生には感謝申し上げます。
そして、受講者の皆さま、お疲れ様でございました。
■京都府精神保健福祉総合センター こころの健康のためのサービスガイド
相談窓口 一覧
http://www.pref.kyoto.jp/health/jisatsutaisaku/jisatsutaisaku10.html

テーマは「グリーフ概論・自死/自殺におけるグリーフ」でした。
グリーフ・グリーフ反応についての概論と基礎的な知識、自死/自殺におけるグリーフを講義され、その後にはグループワークを実施しました。
足利先生の講義の後には、自殺遺族の尾角光美氏(一般社団法人リヴオン代表)が当事者としての内容を、弁護士会・司法書士会の方からは、それぞれの領域で自死/自殺に特化した内容をそれぞれお話されました。多面的に自死を考える大切な場となりました。
受講者の方々は、ゲートキーパー(悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のこと)の方々で、中には臨床心理士の方も多くいらっしゃいました。
ご感想の中で、良かった点として
「初学者でも大変わかりやすい講義でした。」
「ゆっくりていねいに話してもらえてわかりやすかった。」
「事例や実践に基づいた内容で知りたいことを簡潔に資料にまとめていただいていた。」
などのご意見がありました。
今回、お声をいただきました京都府の御関係者、並びに講師をしていただいた足利先生には感謝申し上げます。
そして、受講者の皆さま、お疲れ様でございました。
■京都府精神保健福祉総合センター こころの健康のためのサービスガイド
相談窓口 一覧
http://www.pref.kyoto.jp/health/jisatsutaisaku/jisatsutaisaku10.html
2014/9/8
2014年9月7日 第5回 公開講座が京都グリーフケア協会にて開催されました。

講師は奥野茂代先生
(京都橘大学看護学科非常勤講師、元京都橘大学看護学科教授長野県看護大学名誉教授)
「高齢者の死に対するイメージと安らかな最期を迎えることへの支援」
のテーマで講演頂きました。
先生の話は非常にわかりやすくそして楽しく、あっという間に終わってしまったという受講生が多く、終了時間も予定より延長していましたがもっともっと講義を受けたい、聞きたかったと熱い言葉が聞かれました。
アンケートの一部を紹介します。
「聴くことの原点に立ち戻ることができた、寄り添う気持ちを再認識して実践していきたい」
「コミュニケーション力の大切さに気付かされた。自分でできていると思っていましたが、振り返ると聴くよりは説得していたと気付かされました」
「最期のベストフレンドと思って働いている。その言葉を胸に最期が近い人たち、老年期の患者と関わっていきたい」
講師の奥野先生、そして受講者の皆さま、本当にありがとうございました。

講師は奥野茂代先生
(京都橘大学看護学科非常勤講師、元京都橘大学看護学科教授長野県看護大学名誉教授)
「高齢者の死に対するイメージと安らかな最期を迎えることへの支援」
のテーマで講演頂きました。
先生の話は非常にわかりやすくそして楽しく、あっという間に終わってしまったという受講生が多く、終了時間も予定より延長していましたがもっともっと講義を受けたい、聞きたかったと熱い言葉が聞かれました。
アンケートの一部を紹介します。
「聴くことの原点に立ち戻ることができた、寄り添う気持ちを再認識して実践していきたい」
「コミュニケーション力の大切さに気付かされた。自分でできていると思っていましたが、振り返ると聴くよりは説得していたと気付かされました」
「最期のベストフレンドと思って働いている。その言葉を胸に最期が近い人たち、老年期の患者と関わっていきたい」
講師の奥野先生、そして受講者の皆さま、本当にありがとうございました。
2014/8/26
2014年8月22日 白山先生が、西宮市社会福祉事業団様からのご依頼で、西宮市で開催されたホームヘルパー研修会にて講義を行われました。

講師は、医療法人拓海会 大阪北ホームケアクリニックの院長、白山宏人先生です。
テーマは「在宅におけるグリーフケア」です。グリーフ概論から、在宅事例、患者やご家族とのコミュニケーションのあり方などをお話頂きました。
受講者は主にホームヘルパーの方々で、40名〜50名様にお越しでした。
受講者は先生のお話に頷きながら、時には笑い声も聞かれ、リラックスしたご様子でした。
映像や音楽を織り交ぜつつ、視聴覚に訴える講義で、内容もわかりやすい講義でした。
受講後のご感想として、
「利用者の方々と関わりコミュニケーションをはかる上で、日常から思ってはいたけれど、自分のモノにできていなかった大切なことを改めて教えて頂けた。ありがとうございました。」
などのお声が聞かれました。
今回、ご依頼を頂きました事業団の方々、講師の白山先生、そして、受講者の皆さま、本当にありがとうございました。

講師は、医療法人拓海会 大阪北ホームケアクリニックの院長、白山宏人先生です。
テーマは「在宅におけるグリーフケア」です。グリーフ概論から、在宅事例、患者やご家族とのコミュニケーションのあり方などをお話頂きました。
受講者は主にホームヘルパーの方々で、40名〜50名様にお越しでした。
受講者は先生のお話に頷きながら、時には笑い声も聞かれ、リラックスしたご様子でした。
映像や音楽を織り交ぜつつ、視聴覚に訴える講義で、内容もわかりやすい講義でした。
受講後のご感想として、
「利用者の方々と関わりコミュニケーションをはかる上で、日常から思ってはいたけれど、自分のモノにできていなかった大切なことを改めて教えて頂けた。ありがとうございました。」
などのお声が聞かれました。
今回、ご依頼を頂きました事業団の方々、講師の白山先生、そして、受講者の皆さま、本当にありがとうございました。
2014/8/8
京都グリーフケア協会から8月11日にグリーフケア・ガイドブックが発刊されます。

京都グリーフケア協会から8月11日にグリーフケア・ガイドブックが発刊されます。
一般書店などでは販売しておりません。HPか直接のお電話にて販売しております。
是非お求めください。
グリーフケア・ガイドブックは京都グリーフケア協会で講義を頂いている10人の講師の方々に多大なるご協力を得て、グリーフケアの概論から講師の先生方が実践されてきたグリーフケアに対する深い思いが書かれています。
看護師・助産師コース、介護・福祉従事者コース、葬儀従事者コースの受講生は勿論、グリーフケアを学びたいという方々に是非お読みいただきたいと思います。執筆いただいた講師の先生方の紹介やテーマ、購入方法、費用などは下記をご覧ください。
詳細・申込みページへ
職場などで5冊以上お買求めの方は送料が無料になるサービスもございますのでご利用ください。
全172ページの読み応えある1冊です。

京都グリーフケア協会から8月11日にグリーフケア・ガイドブックが発刊されます。
一般書店などでは販売しておりません。HPか直接のお電話にて販売しております。
是非お求めください。
グリーフケア・ガイドブックは京都グリーフケア協会で講義を頂いている10人の講師の方々に多大なるご協力を得て、グリーフケアの概論から講師の先生方が実践されてきたグリーフケアに対する深い思いが書かれています。
看護師・助産師コース、介護・福祉従事者コース、葬儀従事者コースの受講生は勿論、グリーフケアを学びたいという方々に是非お読みいただきたいと思います。執筆いただいた講師の先生方の紹介やテーマ、購入方法、費用などは下記をご覧ください。
詳細・申込みページへ
職場などで5冊以上お買求めの方は送料が無料になるサービスもございますのでご利用ください。
全172ページの読み応えある1冊です。